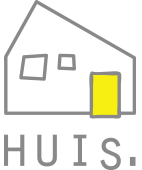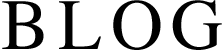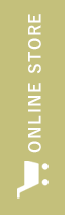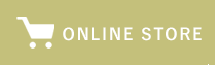浜松出身のライター・宮崎駿(みやざきしゅん)さんが綴る『知らずにいた故郷の誇り、遠州織物の今と未来』、第10回「サイジング」(後編)です。
.
.
.
前回はサイジングの行程について書きましたが、今回はこの技術を支えている業界の現状について、伺ったお話をお伝えします。正直なところ、過去お伝えしている経通し、整経の二つの工程以上に、厳しい状況であると感じました。
まず衝撃を受けたのは、遠州のサイジング工場が、現時点でたったの3社しかないという事実でした。しかも、そのうちの1社が廃業をする可能性が出てきてしまっているとのこと。話を聞き進めるうちに、これは単純に「3分の1が減る」という数の問題ではないことがわかり、より一層現状の課題を目の当たりにしました。
3社はそれぞれ得意分野を持ち、これまでうまく役割分担をしながら遠州織物という産業を支えてきました。中でも廃業予定の工場は、先染めも後染めのどちらも、太番手から細番手まで、小ロットでも量産でも、何でもやれる技術を持っているとのこと。一方、他の2社は主に効率的な一斉サイジングが中心で、先染めに関してはほとんど実施していないそうです。
つまり、この1社がなくなると、遠州産地において小ロット生産をしたり先染めの生地を作ったりすることがとても難しくなってしまいます。遠州織物の土台が、今にも崩れそうになっているんです。

新たにサイジング工場を作るという選択肢も、現実的ではありません。設備投資の大きさ、技術習得にかかる時間、そして何より採算性の問題があります。さらに、前回書いたような過酷な労働環境も、後継者が見つからない大きな要因となっています。
もちろん、ただこの危機を傍観しているわけではなく、新しい動きも生まれているとのこと。これまでの完全な分業制から、それぞれの機屋さんが必要な工程を自社で内製化し行うことで、技術を守っていくという方向性が、1つの選択肢として見えてきているとのことです。
しかし、この対策も簡単にできることではないようです。まず、単純に機屋さんが事業拡大することには経営上大きなリスクを伴います。また、内製化をした場合でも、一つの工程だけでは安定した仕事量が確保できないため、担当者は複数の技術を身につける必要があります。つまり、サイジング職人として専門特化するのではなく、整経なども含めて複数の技能を持つ職人を育てるという新しいあり方が模索されています。
分業制は効率的である一方、こうした危機の時にはその脆さが露呈します。でも逆に考えれば、各社が技術を内製化することで、より強い産地になれるかもしれません。ピンチをチャンスに変える、まさにそういう転換期なのかもしれません。
業界全体でも、この危機への対応を日々考え尽くし、それぞれができることから始めています。

ただ、悲観的な話ばかりではありません。「以前遠州織物の世界に飛び込んでくれた方が、最近職人として独立しました。その方は織物産業の奥深さに魅力を感じ、もっと深く関わっていきたいと話してくれているんです」と松下さん。他にも、遠州産地のプロジェクトチーム「entrance」が主催した、遠州織物の世界を体験するイベントへの参加をきっかけに、この世界に飛び込んでくる人たちが現れ始めているとのこと。

その方々の気持ちはよくわかります。私もこの連載を始めるまでは、遠州織物については何も知らない人間の一人でした。でも、知れば知るほどその奥深さに惹かれて、知りたいことが増えていく。そういう入口を作ることの大切さを、改めて感じます。現状はまだ小さな動きかもしれませんが、確実に変化の兆しは見えています。
今回の取材で見えてきたのは、サイジングが抱える構造的な問題でした。3社しかない工場のうち1社が廃業の危機に追い込まれており、貴重な遠州の技術が一度にたくさん失われようとしている。そして新規参入は難しく、既存の工場も後継者不足に悩んでいる。これらの問題が複雑に絡み合い、産地全体が大きな岐路に立っています。
しかし同時に、この状況を何とかしようと奮闘する人たちの姿も見えてきました。内製化という新しい方向性、複数技能を持つ職人の育成、そして何より、繊維の魅力に惹かれて入ってくる新しい人材。小さな一歩かもしれませんが、確実に前に進んでいます。
3社から2社へ。この数字の変化は、遠州織物の大きな特色が失われつつあることを意味します。目を背けたくなるカウントダウンなのかもしれません。それでも諦めている人は誰もいません。むしろこの危機を乗り越えるために、それぞれが新しい道を模索している。その姿に、遠州織物の底力を見た気がします。