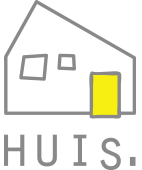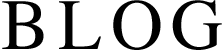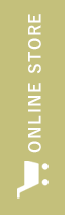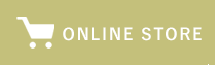浜松出身のライター・宮崎駿(みやざきしゅん)さんが綴る『知らずにいた故郷の誇り、遠州織物の今と未来』、第8回「手作業 」です。
.
.
.
これまで遠州織物について書く中で、何度も「手作業」という言葉が出てきました。分業制で成り立っていること、大量生産ではなく小ロット生産が中心であること、そして前回書いた整経のように、機械化できない工程が複数あること。正直なところ、どこかで「もっと効率的にできないのかな」という疑問と、「この時代に、よくそのスタイルで産業が成り立つな」という驚きが頭をよぎることがありました。
特に印象的だったのが整経の話でした。何千本もの糸を、一本一本手で並べていく。その一本一本に均等な張りを持たせながら、決められた順番通りに巻き取っていく作業。フリーランスのライターとして、普段から一つ一つの原稿を大切に書くことを心がけていますが、時には効率を意識せざるを得ない場面もあります。そういった立場でもあったため、効率化という選択肢を選ばないことに対する疑問は、どんどん強まっていきました。
でもその疑問は、「大きな産地では機械化が進んでいます。でも遠州では、小規模事業者が多く、機械を導入するコストも現実的ではない。そして何より、手作業だからこそ生まれる価値があるんです」という松下さんの言葉で解消されました。

この「手作業だからこそ生まれる価値」という言葉の意味が、後になってじわじわと理解できるようになりました。実際、遠州織物が世界的に評価されている理由を考えてみると、それは大量生産や低コストではありません。過去の投稿で書いたように、世界的なブランドが長年頼りにし続けているのは、職人の技術と、手仕事ならではの品質です。
整経の作業工程を動画で拝見した時、その丁寧な手捌きに驚きました。一本一本の糸を確認し、張りを調整し、正確に並べていく。何百本、何千本という糸と向き合いながら、一つのミスも許されない緊張感の中で作業を進めていく職人さんの姿。そこには、効率化された工場では決して見ることのできない、時間をかけてでも確実に仕上げるという姿勢がありました。この一つ一つの積み重ねが、遠州織物の品質を支えているんだと認識しました。
ふと自分の周りを見渡してみると、仕事の場でも、生活の場でも、あらゆるところで効率化が行われています。AIを活用したビジネスツール、コンビニの無人レジやQR決済などなど。気がついた時には当たり前になっており、それ以前の手間のかかる生活を思い出せないようになっていました。
でも時々、何でもかんでも効率化すればいいのだろうかと考えることがあります。たとえば居酒屋に行った時。最近はQRコードでメニューを読み取り注文する、というシステムのお店も増えてきました。これは店側にとっても、客側にとっても効率という観点ではメリットがあるシステムだと思います。ですがシステム化されすぎていることに、なんとなく寂しい気持ちになる人もいるのではないでしょうか?

手作業で作られたものに触れた時の温もりや安心感。遠州織物は、そんな感覚を思い出させてくれる存在なのかもしれません。
特にビジネスの場では、マルチタスクやタイパという言葉も、ここ数年で当たり前に使われるようになりました。複数の仕事を同時進行し、いかに時間対効果を高めるか。今後は、こういった傾向がより顕著になっていくのかもしれません。
でも、そんな時代だからこそ、あえて立ち止まって考えてみることも必要なのかもしれません。効率化を追求することは確かに大切です。でも、目の前にある一つの仕事にじっくりと向き合い、時間をかけて丁寧に仕上げることにも、それと同じくらい大切な価値があるのではないでしょうか。
私自身、ライターとして文章を書く時、早く仕上げることよりも、一文に対して思いを込めることを大切にしたいと改めて思いました。読者の顔を思い浮かべながら、言葉を選び、推敲を重ねる。そんな「非効率」な時間こそが、本当に伝わる文章を生み出すのかもしれません。
以前書いた浜松の産業構造の話を思い出します。効率的な大企業がある中で、小規模な織物職人たちは、あえて手間のかかる道を選び続けました。松下さんは「それだけ価値のあるものだからこそ」と表現していました。
今なら、その言葉の意味をもう少し理解できる気がします。効率では測れない価値。それは、ただ時間をかけるということではなく、その時間の中で職人さんが糸と向き合い、細かな調整を重ねていく。そうやって生まれる確かな品質と、着る人への心配りなのかもしれません。
地元にこんな産業があることを、28歳まで知らなかった私。今は、この話を少しでも多くの人に伝えられたらと思っています。効率がすべてではないということ。時間をかけることにも意味があるということ。遠州織物は、そんな当たり前だけど忘れられかけていることを、ただ静かに続けているだけなのかもしれません。